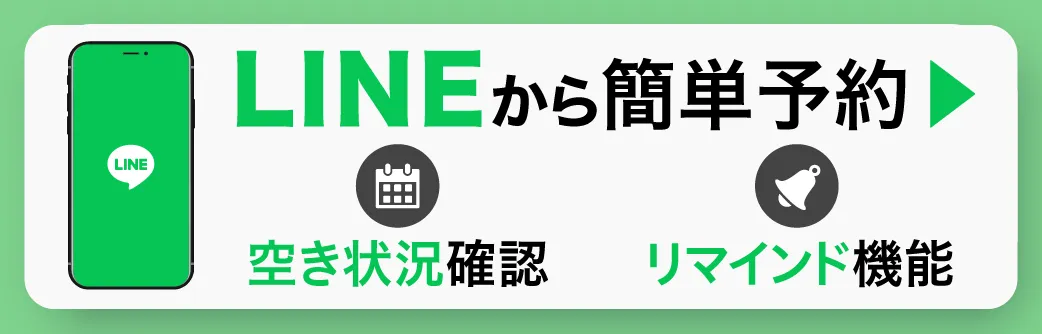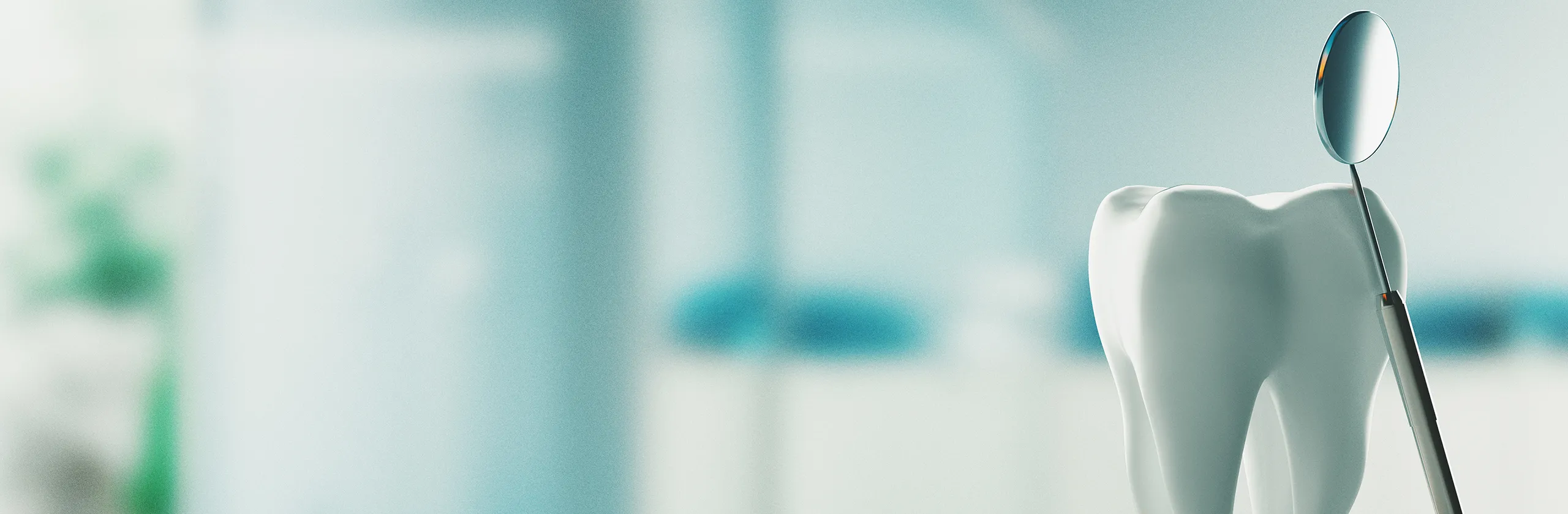入れ歯は、大きく分けて「総入れ歯」と「部分入れ歯」の2種類があり、さらに保険適用と自費診療で使用できる素材や設計、費用が大きく異なります。
この記事では、入れ歯の種類とそれぞれの特徴、費用相場を紹介。さらに、あなたに合ったなれ歯を選ぶための5つのポイントも解説しますので、ぜひ参考にしてください。
入れ歯の種類は大きく分けて2つ
入れ歯には、大きく分けて「総入れ歯」と「部分入れ歯」の2つの種類があります。
総入れ歯
総入れ歯は、上あご、下あご、または上下両方のあごの失われた歯全体を補うものです。
人工の歯と歯ぐきに似せたピンク色の土台(床:しょう)で構成されています。上あごの総入れ歯は、口蓋(上あごの天井部分)を覆うように、広い床を持つ形をしています。一方、下あごの総入れ歯は、舌の動きを妨げないようU字型になっています。
総入れ歯は、お口の中の粘膜に吸着させることで安定させます。
部分入れ歯
1本でもご自身の歯が残っている場合は、「部分入れ歯」が用いられます。部分入れ歯は、失われた歯の部分だけを補うものです。
人工の歯と床に加え、残っている歯に固定するための「クラスプ」と呼ばれる留め金で構成されます。クラスプは金属製が一般的ですが、近年では、目立ちにくい素材を用いた「ノンクラスプデンチャー」と呼ばれる種類の部分入れ歯も選べるようになりました。
部分入れ歯は、残っている歯に支えを求めるため、総入れ歯に比べて安定しやすい傾向にあります。しかし、残っている歯の状態によっては、負担が大きくなる可能性もあります。
【保険適用】入れ歯の種類と費用相場
保険適用の入れ歯の大部分は、「レジン」と呼ばれる歯科用プラスチックです。床(歯ぐきの部分)は、主にPMMA(ポリメチルメタクリレート樹脂)という種類のレジンで作られています。人工歯にも硬質レジンと呼ばれるプラスチックが使用されます。部分入れ歯の場合、残っている歯に固定するためのクラスプ(留め金)には、コバルトクロム合金などの金属が用いられることが多いです。
保険適用の入れ歯のメリットは、自己負担額が1割から3割で済むため、費用が安く抑えられる点が挙げられます。
また、比較的短期間(数週間程度)で完成するため、早く入れ歯が欲しい方にも適しています。さらに、破損や不具合が生じた場合でも修理や調整が比較的容易である点もメリットです。多くの歯科医院で取り扱っており、ほとんどの症例に対応できるという点も心強いでしょう。
一方、デメリットとしては、プラスチック素材であるため、天然の歯と比べると透明感や色調の再現性に限界がある点が挙げられます。
また、部分入れ歯の場合、金属製のクラスプが見えてしまうことがあるため、見た目を気にされる方にはデメリットとなるかもしれません。費用は、あくまで目安ですが、失った歯の本数やお口の状態によって変わってきます。以下は、3割負担の場合の費用の目安です。
- 部分入れ歯の場合:5,000円〜15,000円程度
- 総入れ歯の場合:15,000円程度
失った歯の本数が多い場合(例えば10本以上など)は、設計が複雑になるため、費用が高くなる傾向があります。詳細な費用については、歯科医院で直接ご相談ください。
【自費診療】入れ歯の種類と費用相場
自費診療の入れ歯は、保険診療の入れ歯と比べて使用できる材料や設計の自由度が高く、さまざまな種類があります。天然歯に近い色調や透明感を再現でき、装着感や機能性を追求することも可能です。ここでは、主な自費診療の入れ歯の種類、それぞれの特徴と費用の目安について説明します。
金属床義歯
金属床義歯は、床(歯ぐきの部分)に金属を使用した入れ歯です。金属は強度が高いため、薄くても割れにくく、長期間の使用に耐えることができます。また、薄く作れるため、装着時の違和感が少なく、食べ物の温度を感じやすいというメリットもあります。
費用の目安は、20万円~50万円程度です。
シリコーン義歯
シリコーン義歯は、床部分に柔らかいシリコーン素材を使用した入れ歯です。クッション性があり、吸着力が高いため歯ぐきへの負担を和らげる効果が期待できます。代表的なものに「コンフォートデンチャー」があります。
費用の目安は30万円~60万円程度です。
ノンクラスプデンチャー
ノンクラスプデンチャーは、部分入れ歯で用いられる金属のクラスプを使わない入れ歯です。ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂などを使用することで、金属アレルギーの心配がなく、見た目も自然です。
費用の目安は15万円~40万円程度です。
アタッチメント義歯
アタッチメント義歯は、残っている歯、またはインプラントに、アタッチメントを取り付け、入れ歯を固定する方法です。アタッチメントは、磁石、ボール、ロケーターなど、さまざまな種類があります。入れ歯の安定性が高く、しっかりと噛めるようになることが期待できます。
費用の目安は、アタッチメントの種類によりますが、20万円~50万円程度で、これに入れ歯自体の費用が加わります。
インプラントオーバーデンチャー
インプラントオーバーデンチャーは、顎の骨に埋め込んだインプラントに入れ歯を固定する方法です。インプラントが入れ歯をしっかりと支えるため、安定性や噛む力が大幅に向上します。
費用の目安は50万円からです。
コーヌスクローネ
コーヌスクローネは、残っている歯に金属の被せ物をして、その上からさらに入れ歯を被せる方法です。被せ物は二重構造になっており、茶筒のふたのように摩擦力で入れ歯を固定します。残っている歯を削る必要がありますが、バネがないため見た目が良く、安定性も優れています。
費用の目安は1本あたり10万円~30万円程度で、これに入れ歯自体の費用が加わります。
自分に合った入れ歯の選び方

ここでは、ご自身に合った入れ歯を選ぶためのポイントを5つの視点から紹介します。
予算(保険適用か自費か)
入れ歯治療には、保険診療と自費診療の2つの選択肢があります。
保険診療の入れ歯は、自己負担額が1~3割と費用を抑えられるのがメリットです。しかし、使用できる素材や設計には制限があります。一方、自費診療の入れ歯は、費用は高額になりますが、高品質な素材を選べ、精密な設計が可能です。見た目、機能性、快適性、耐久性など、ご自身のこだわりを追求したい場合に適しています。
どちらを選ぶかは、目先の費用だけでなく、修理や作り直しの可能性も考慮し、長期的な視点で費用対効果を考えることが大切です。
見た目(自然さ、目立たなさ)
人から見えやすい部分に入れ歯を入れる場合は、特に見た目が気になるものです。
歯科医院で、サンプルや症例写真を見せてもらい、仕上がりのイメージを確認しましょう。自費診療であれば自然な色合いや透明感を再現できる素材を選ぶことも可能です。
機能性(噛み心地、発音のしやすさ)
「硬いものをしっかり噛みたい」「柔らかいものを中心に食べたい」など、食事の好みは人それぞれです。また、アナウンサー、歌手、教師など、発音を重視する職業の方にとっては、入れ歯が発音に影響を与えないかどうかも重要なポイントです。
快適性(違和感、痛み)
過去に入れ歯で痛みや違和感を覚えた経験がある方は、特に慎重に入れ歯を選びたいものです。口の中が敏感な方や嘔吐反射が強い方は、その旨を歯科医師に伝え、相談しながら作成ましょう。試適ができる場合は、装着感や痛みがないかをしっかりと確認することが大切です。
耐久性(長く使えるか)
長く使用出来る入れ歯を希望される場合は、耐久性の高い素材を選ぶことが大切です。また、将来的な修理や調整がしやすいかどうかも、歯科医師に確認しておきましょう。
入れ歯に関するよくある質問(Q&A)
入れ歯について、患者様からよくいただくご質問とその回答をまとめました。
Q1:保険の入れ歯と自費の入れ歯、どっちがいい?
A1:一概にどちらが良いとは言えません。それぞれにメリット・デメリットがあり、お口の状態、予算、ライフスタイル、何を重視するかによって選択肢は異なります。
Q2:入れ歯の寿命はどれくらい?
A2:入れ歯の寿命は使用している素材、日頃のお手入れの方法、使用状況、お口の状態など、さまざまな要因によって大きく異なります。一般的な目安としては保険診療の入れ歯で3年~5年程度、自費診療の入れ歯であれば5年~10年以上と言われています。
Q3:医療費控除は受けられる?
A3:はい、入れ歯の治療費は医療費控除の対象となります。これは、保険診療で作製した入れ歯、自費診療で作製した入れ歯のどちらでも同様です。
まとめ
入れ歯には、総入れ歯と部分入れ歯があり、それぞれ保険適用と自費診療の選択肢があります。保険適用の入れ歯は費用を抑えられますが、素材や設計に制限があります。一方、自費診療の入れ歯は様々な種類があり、見た目や機能性など、自分の希望に合わせた入れ歯を選択できます。
自分に合った入れ歯を選ぶためには、予算や機能性、快適性、耐久性などを考慮し、歯科医師とよく相談することが大切です。