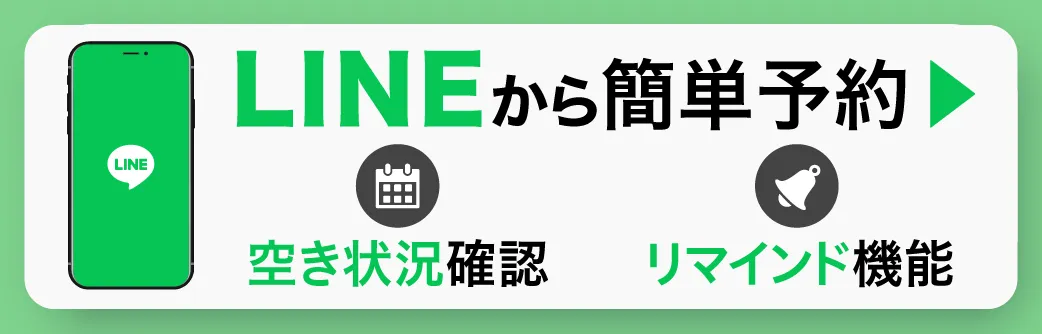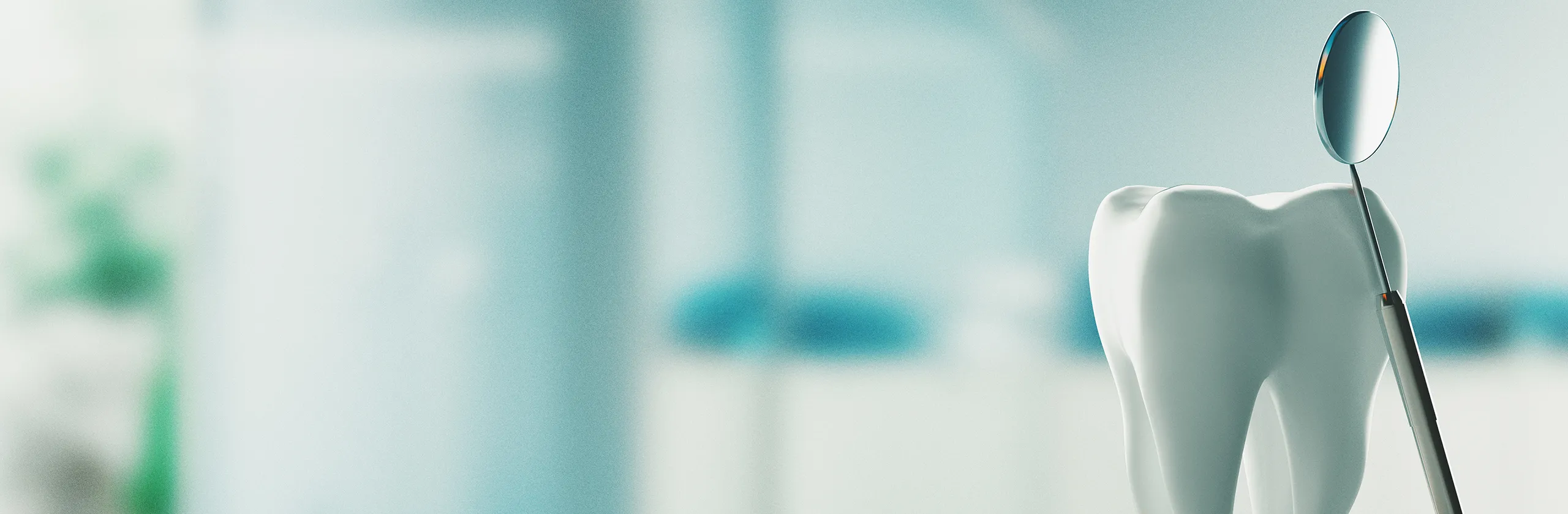「もしかして、これって虫歯…?」
「最近、冷たいものが歯にしみる…」
「甘いものが好きだけど、虫歯になりやすいのかな?」
こんな風に、ご自身の歯について不安を感じたことはありませんか?
虫歯は、お口の中で起こる最も身近なトラブルの一つですが、その原因や進行のメカニズムは知らない方も多いのではないでしょうか。
虫歯は、「虫歯菌」「糖質」「歯の質」「時間」という4つの条件が重なることで発生します。そして、日々の食生活や口腔ケアの習慣、唾液の量や歯並びといった特徴も虫歯のなりやすさに大きく関わっています。
この記事では、虫歯がどのようにしてできるのか、根本的な原因となりやすい人の特徴、そして虫歯の進行段階ごとの症状について解説します。
虫歯が発生する4つの条件
そもそも虫歯とは、お口の中にいる細菌が作り出す酸によって、歯が溶かされてしまう病気のことです。虫歯は、以下の4つの条件が重なったときに発生します。
条件1:虫歯菌(ミュータンス菌など)の存在
お口の中には様々な細菌がいますが、中でも「ミュータンス菌」と呼ばれる種類の菌が虫歯の主な原因菌です。
これらの細菌は歯の表面にくっつき、「歯垢(プラーク)」というネバネバした塊を作ります。そして、歯垢の中でどんどん増えながら食べ物に含まれる糖分を分解して「酸」を作り出します。
条件2:糖質(砂糖など)の摂取
糖質は、虫歯菌が活動するためのエネルギー源、つまりエサになります。特に、お菓子やジュースに多く含まれる砂糖(ショ糖)は、虫歯菌が酸を作るために利用しやすい糖質です。
食べ物や飲み物に含まれる糖質がお口の中に残っている時間が長ければ長いほど、虫歯になるリスクは高まります。
条件3:歯の質
歯の硬さや歯並び、奥歯の溝の深さなども虫歯のなりやすさに関係します。
また、唾液もお口の健康を守る大切な役割を担っています。唾液には、虫歯菌が作り出した酸を中和する力(緩衝能)や、お口の中の汚れを洗い流す作用があります。そのため、生まれつき歯質が弱い方、唾液の量が少ない方、歯並びが悪くて磨き残しが多い方などは、虫歯になりやすい傾向があります。
条件4:時間の経過
上記の「虫歯菌」「糖質」「歯の質」の3つの条件がそろった状態が、どれくらいの時間続くかという点も重要です。
虫歯菌が糖質から酸を作り、その酸によって歯の表面からミネラル成分が溶け出す現象(脱灰:だっかい)が進むには、一定の時間が必要です。
食事やおやつの回数が多かったり、時間を決めずにだらだらと食べ続けたりすると、お口の中が酸性の状態になっている時間が長くなり、虫歯が進行しやすくなります。
虫歯の主な原因

虫歯の発生には、日々の生活習慣が大きく関わっています。具体的にどのようなことが原因となるのか見ていきましょう。
食生活が原因の場合
甘い飲食物を頻繁に摂ったり、時間を決めずにだらだらと食べたり飲んだりする習慣、酸性の強い飲食物の過剰な摂取は、お口の中が歯の溶けやすい環境になる時間を長くするため、虫歯の主な原因となります。
口腔ケアが原因の場合
毎日の歯磨きが不十分で歯垢が残っていたり、歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間のお手入れを怠ったりすることも虫歯を引き起こす直接的な要因になります。
唾液が原因の場合
お口の汚れを洗い流し酸を中和する唾液の量が減ることや、その質(酸を中和する力)が低下することも虫歯が発生しやすい状態を招きます。
歯や口内環境が原因の場合
歯並びが悪く清掃しにくい部分があったり、過去の治療箇所が劣化したり、歯ぐきが下がって歯の根が露出したり、生まれつき歯質が弱かったりすることも、虫歯になりやすい要因として挙げられます。
虫歯の進行とそれぞれの症状
虫歯は深さによって段階的に進行し、症状も変化していきます。進行度合いは一般的に「C」と数字で表されます。
C0:初期虫歯(要観察歯)
歯の表面が白く濁ったように見えることがありますが、まだ穴は開いていません。この段階では、痛みなどの自覚症状はほとんど感じられないでしょう。適切なケアによって健康な状態に戻る可能性もあります。
C1:エナメル質の虫歯
歯の一番外側にある硬い層「エナメル質」が溶け始めた状態です。見た目の変化はわずかで痛みを感じることはまだ少ないです。
C2:象牙質の虫歯
虫歯がエナメル質の下にある「象牙質」まで進んだ段階です。象牙質はエナメル質よりも軟らかいため、虫歯の進行が早まることがあります。
冷たいものや甘いものを口にしたときに、歯がしみるといった症状が出始めます。
C3:神経(歯髄)まで達した虫歯
虫歯がさらに深く、歯の中心部にある神経や血管(歯髄)まで達してしまった状態です。何もしなくてもズキズキと強い痛みを感じたり、熱いものがしみたりするようになります。
ここまで進行すると、歯の神経を取り除く治療が必要になる可能性が高いです。
C4:歯根だけ残った状態(残根)
虫歯によって歯の見える部分(歯冠)がほとんどなくなり、歯の根っこ(歯根)だけが残ってしまった状態を指します。
歯の神経が死んでしまうと、一時的に激しい痛みは治まることもあります。しかし、放置すると歯根の先に膿が溜まって歯ぐきが腫れたり、再び痛みが出たりするリスクがあります。
虫歯ができやすい場所
お口の中には構造的に汚れが溜まりやすく、虫歯になりやすいとされる場所があります。
- 奥歯の噛み合わせ面にあるの溝(小窩裂溝)
- 歯が隣り合っている面(隣接面)
- 歯と歯ぐきの境目(歯頸部)
- 治療で詰めた物や被せた物とご自身の歯との境目
- 歯の根元(根面)※特に歯茎が下がっている場合
これらの場所は、毎日の歯磨きで特に意識したいポイントです。鏡を見ながら1本ずつ磨いていきましょう。
こんな方は要注意?虫歯になりやすい人の特徴
以下のような習慣や特徴をお持ちの方は、そうでない方と比べて虫歯になるリスクが高いと考えられます。ご自身の生活習慣を振り返ってみましょう。
- 甘いものを頻繁に口にする方
- 口腔ケアが不十分、または苦手な方
- 口が乾きやすい(唾液が少ない)方
- 歯並びに問題がある方
- 過去に虫歯治療を多く受けている方
- 歯科検診に長期間行っていない方
今日からできる虫歯予防
虫歯は、毎日の心がけとケアで予防することが可能です。ここでは、ご自身でできるセルフケアと、歯科医院で受けるプロケアについて紹介します。
【セルフケア編】毎日の習慣で虫歯を防ぐ

虫歯予防の基本は、毎日のセルフケアです。正しい方法での歯磨きはもちろん、デンタルフロスや歯間ブラシを使って、歯と歯の間の歯垢までしっかり落としましょう。また、フッ素配合の歯磨き粉などを効果的に使い、歯を強くするのもおすすめです。
虫歯予防には、食生活の見直しも欠かせません。糖分の多い間食を控えたり、時間を決めたりするなど、糖分の摂取を意識しましょう。
唾液にはお口の中をきれいにする働きがあります。食事の際によく噛むなど、唾液の分泌を促す工夫も大切です。
【プロケア編】歯科医院で受ける専門的な予防

セルフケアだけでは防ぎきれない虫歯リスクには、歯科医院でのプロケアが有効です。
普段の歯磨きでは落としきれない歯垢や歯石を専用の機器で除去する「スケーリング」や、虫歯予防に効果的な高濃度フッ素塗布、お子さんの奥歯の溝を埋めるシーラント処置(※)で虫歯になりにくい強い歯を作ります。(※シーラント:虫歯になりやすい奥歯の溝を、あらかじめ歯科用プラスチックで埋める処置)
また、歯科医院によっては唾液検査などでお口の状態や虫歯リスクを評価してくれるところもあります。プロケアは3ヶ月~半年に一度、継続して受診すると効果的に虫歯を予防できるでしょう。
まとめ
虫歯は、C0からC4まで段階的に進行し、放置すると強い痛みが出たり、最終的には歯を失う原因にもなりかねません。特に、奥歯の溝や歯と歯の間、歯ぐきの境目などは汚れが溜まりやすく、注意が必要です。
しかし、毎日のセルフケアを見直し、定期的に歯科医院でプロケアを受けることで、虫歯のリスクを大幅に減らすことができます。大切な歯を守るために今日からできることからはじめて健康なお口を維持していきましょう。